
赤ちゃんとのおでかけは、生後一か月健診が済んだころから、少しずつ始めていくのが一般的です。
近所でのお散歩から始まり、慣れてきたら車や電車に乗って。
赤ちゃんの月齢により、また移動距離や時間がのびていくにつれて、お悩みや工夫ポイントはさまざま。
まずは、専門家におでかけのキホンを教えていただきましょう。
専門家:福井聖子(小児科医)
【目次】
・赤ちゃんとお出かけするメリットは?
・感染症にはどこまで気をつければいい?
・お出かけはいつから?時間の目安は?
赤ちゃんとおでかけするメリットは?
自律神経や体内時計、「感じる力」の発達を促す
乳幼児期は、心と体がグンと成長するとき。外に出て刺激を受けることで、体温調節などに関する自律神経や体内時計などが整います。また、太陽の光は近視の予防にも効果があるほか、「暑い」、「寒い」、「風が気持ちよい」など、外気そのものに触れる体験は「感じる力」の発達に大きく影響します。小さいうちから親子で外出する機会をなるべくつくりましょう。(福井聖子さん)
※外出するときは強い日ざしを避け、過ごしやすい時間帯を選びましょう。
言葉がけによって「感じたこと」と「ことば」がつながる
例えば暑いとき、赤ちゃんの体は赤くなったり、汗をかいたりしますね。赤ちゃんの自律神経が調整をおこなっているのです。そのときがチャンス。赤ちゃんの顔を見ながら「暑いね」などと言葉をかけると、「暑い」がどんなことなのかが赤ちゃんにもだんだんわかってきます。屋外には、赤ちゃんがそういったことを感じるチャンスや刺激がたくさんあります。(福井聖子さん)
感染症にはどこまで気をつければいい?
毎日、食材の買い出しなどのため、3か月の息子と一緒に外出しています。寄り道をしたり、友人と会ったりして、2時間以上の外出になることもあります。感染症が心配で、繁華街を抜けるときなどはベビーカーのひさしを下げるなどしていますが、赤ちゃんとおでかけするときの感染症対策はどうしたらよいのでしょうか。
生後4か月くらいまでは感染症からある程度守られている
ニュースで「〇〇感染症がはやっている」などと聞くと心配になりますよね。赤ちゃんは、ある程度守られています。お腹の中にいるときに、お母さんの胎盤を介して受け継いだ抗体が生後4~6か月頃まで体内にあり、また母乳にも免疫物質や免疫を高める栄養素が入っています。そのため、生後2~4か月くらいまでは、意外と感染症が少ないのです。屋外での散歩ていどであれば、感染症を心配する必要はありません。(福井聖子さん)
赤ちゃん、家族ともに基本的な感染対策を
ある程度守られているとはいえ、赤ちゃん自身がそこまで強い力を持っているわけではありません。赤ちゃんや小さい子どもとの外出では基本的な感染対策が大切です。
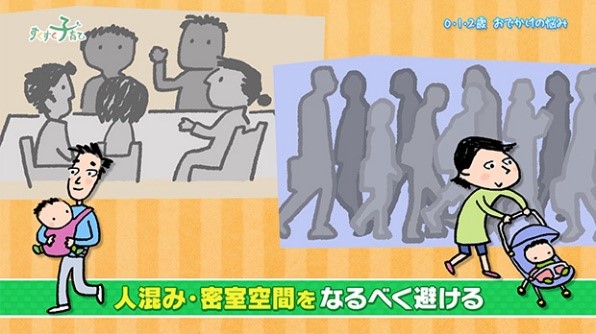

1.人との距離が近い、人混みや密室空間をなるべく避ける。
2.赤ちゃんと生活を共にする家族も、人混みを通るときはマスクをしたり、こまめに手を洗ったり、基本的な感染対策を行う。
そばにいる大人が普段から外出時の感染対策を欠かさないことも、子どもの感染予防にはかかせません。(福井聖子さん)
おでかけはいつから?時間の目安は?
生後1か月以降、赤ちゃんのサインをキャッチして
生まれてすぐの赤ちゃんは、お腹の中から外に出たばかりなので、外気に慣れるのが大変です。体温調節や呼吸などの機能が未熟なので、外出は環境に順応する生後1か月以降少しずつがいいでしょう。赤ちゃん自身があちこちを見るような、「刺激を受けたい」サインが見られるようになったら少しずつ外に出てみましょう。(福井聖子さん)
3~4か月以降は赤ちゃんの様子を見ながら時間を調整
3~4か月になると、赤ちゃんの機嫌もわかるようになります。外出が負担になっている場合は、いつもより眠りにくい、母乳・ミルクを飲む量が減るなどの変化があります。そのような様子を見ながら、外出時間を調整してみましょう。(福井聖子さん)
©NHK
※本記事は、 NHK 「すくすく子育て」のホームページの記事を元に構成・編集・加筆しています。記事を読んでもっと知りたいことがありましたら、ぜひ「マムアップパーク by 健幸スマイルスタジオ」にご参加ください。お待ちしています!
